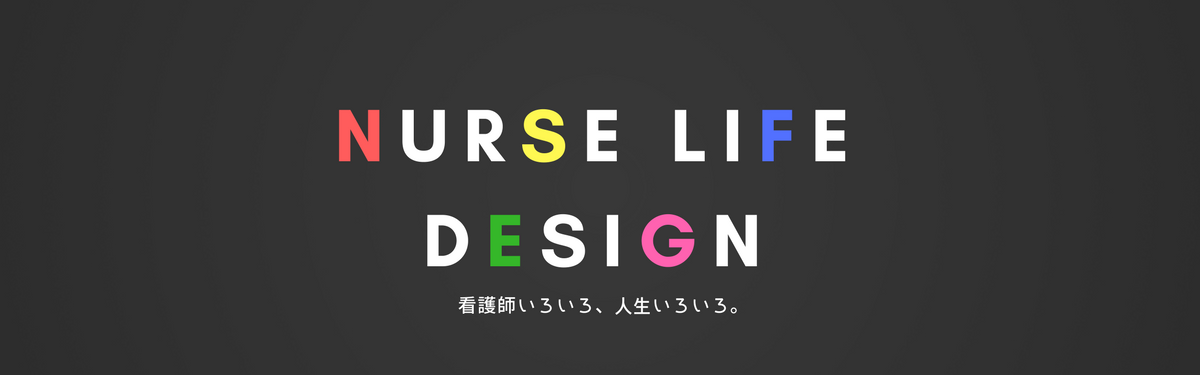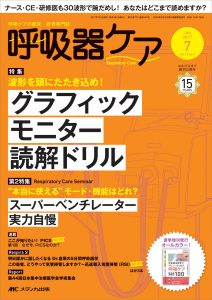
どうも、ナースヒーロー 西 英雄です。
ご覧いただきありがとうございます。
1か月が過ぎるのを早いと感じるか、
遅いと感じるかは人それぞれです。
意識的な行動が多ければ多い程、
その1か月は長く感じるのではないかと思います。
無意識=ゾンビ状態
意識的に行動するということは、
ある意味「我慢」なのでツライです。
しかし、
「居心地の悪い場所にしか成長はありません」
そんな感じで(どんな感じなんだ・・・)
「呼吸器ケア2017.7」の感想を、今回もまとめていきたいと思います。
【特集】グラフィックモニター読解ドリル
最近の人工呼吸器では、
もはやグラフィックモニターが当たり前となっています。
それに伴って看護師にも、
波形やループを読み解く力が求められます。
ICUやHCUじゃないから関係ないとか、
そんな時代はとっくに終わっています。
一般病棟でも呼吸器病棟なら当然ですし、
外科や神経内科など人工呼吸器管理はどこでも必要とされています。
在宅看護でも然り・・・
いずれはグラフィックモニター付きの在宅人工呼吸器が
当たり前の時代になるかもしれません。
時代と医療が進歩し続ける限り、
私たち看護師も学び続けなければいけないという事。
そんなことを改めて思い知らされる7月号でした。
特集は「グラフィックモニター読解ドリル」
実際に文章や書面で問題を出されると、
結構難しいですね。
完璧な正解はほとんどありませんでした(笑)
私たちが人工呼吸器のアラームが鳴って対応する時は、
もちろん波形を見て判断することもあります。
ですが基本的には患者さんの状態を診て、
色々試して問題を解決していきます。
もちろんそれで充分なのかもしれませんが、
それはアラームが鳴ることが大前提です。
要は患者さんが悲鳴をあげてからしか、
こちらは異常に気が付かないし行動しないという事。
そう考えると看護師としては物足りませんよね。
アラームというのは結局のところ、
こっちが勝手に決めた最低ラインです。
人工呼吸器管理中の患者でも、
可能な限り安楽を支援できる。
そんな看護の為にグラフィックモニターの読解が役立つのだと、
痛感しながら問題に挑戦していました。
改めて人工呼吸器のモードや設定のイロハ、
異常時の呼吸生理など勉強になりました。
これで実際にグラフィックモニターに触れる現場にいたら、
さらに学びが深まるのにな〜と思います。
やはりインプットとアウトプットは、
セットでなければ意味がないです。
アウトプットする場が無ければ、
自分の血肉にはなってくれません。
なので是非グラフィックモニターを学ぶときは、
実際に人工呼吸器も見ながらやってほしいと思います。
今回の特集を読んでみて、
グラフィックモニター攻略のポイントを私なりにまとめてみました。
グラフィックモニター攻略ポイント
こんな感じですかね、
参考にして頂けたら嬉しいです。
この特集を読んでも多分、
グラフィックモニターが読めるようになりません。(苦笑)
ですがこれをきっかけに人工呼吸器に関する知識が増えたり、
今までの復習として質が向上することは間違いないです。
「勉強→行動」の流れが作りにくい分野ではありますが、
チャレンジしてみる価値は絶対にある!!
そんな特集記事でした。
【第2特集】スーパーベンチレーター実力自慢
2つ目の特集はちょっとオタクレベルです(笑)
この特集を読んで喜ぶ人もいるのでしょうか、
MEさんとか相当なベンチレーター好きとか・・・
最新の人工呼吸器が5台、
詳細にそのスペックや特徴が説明されています。
人工呼吸器もどんどん進化を続けていて、
”より安全かつ快適な呼吸をどうアシストするか”を追求しています。
その進歩は本当にスゴ過ぎて、
「逆に医者や看護師がいらなくなってしまうのでは?」
と思うくらいでした。
そんな私にとって激ムズの特集でしたが、
勉強になったことをまとめます。
最新ベンチレーターの恐るべき能力まとめ
などなど目から鱗の内容や、
ちょっとゾッとする近い未来を想像しました。
自分は看護師としてどの視点から人工呼吸器と渡り合っていくのか、
「患者さんにどんな形で貢献できるのか」ということを改めて考えさせられました。
私が3次救急を離れたということもありますが、
本当に知らない事ばかりでした。
是非気になる方は読んでみてください。
以上が 「呼吸器ケア2017.7」の感想です。
さすがに明日の訪問看護には直接役に立ちませんが、
それでも最新の動向を知るのは看護師として重要です。
そしてどんな形でもいいから、
その学びをアウトプットに繋げる。
8月号も読み進めていますので、
また感想を記事にまとめていきたいと思います。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございます。
次回またお会いしましょう。
余談ですが・・・
7年目から訪問看護師になりました。
そんな心境を詰め込んだ記事を貼らせていただきます。
→「※参考記事:勉強する人もしない人も、看護師なら見てください」
ご興味があれば見てやってください(笑)
そして訪問看護師になった時の心境はコチラです。
→「※参考記事:訪問看護師になろうとする今・・・」
ありがとうございました。
☆こちらの記事もそこそこ読まれています☆